【民泊許可申請シリーズ③】消防法について
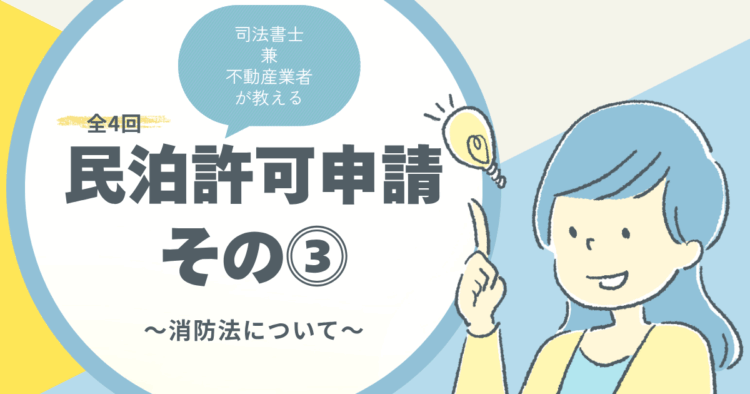
民泊の申請で一番重要で大変なのが、消防関連の申請です。なお、消防については、民泊も簡易宿所も基本的に同じ申請内容になります。
普通の住宅を民泊にしようとする場合、どの家にも火災報知器や消火器はあるのでは? と思いますよね。ところが、住宅用の設備で申請できるのは、一軒家で家主が不在とならない、かつ宿泊室(寝室)が50㎡以下である場合のみに限られています。この条件以外で民泊をしようとする場合は、事前に消防に相談し、必要な設備を揃え、「消防法令適合通知書」を消防から交付してもらわなければいけません。
消防法令適合通知書は、添付書面ではない?
前回の記事を参照していただきたいのですが、実は「消防法令適合通知書」は添付書面にはなっていません。しかし、自治体によって許可証受領までのタイミングで提出か提示をしなければならないことが多いですし、そもそも消防法令に適合している施設であることが申請の前提条件となります。
民泊や旅館業の申請自体は通知書がなくても可能なのですが、添付書面にないからといって何もせずにおくと、いざ見せてくださいと言われたときに間に合わず、開業が大きく遅れてしまう可能性がありますので注意が必要です。
申請方法
まず、立面図・各階平面図・設備配置図等の図面一式を持って消防に相談に行きます。外観や室内の写真などもあると良いでしょう。
すると、どこにどういった種類の設備を設置する必要があるか、消防の担当者が細かく教えてくれます。
必要に応じて工事や物品の購入を行い、消防の指示通りに設置が終わったら、消防に通知書交付のための申請をします。
申請書類を提出したら、消防による立会検査が行われた後に、通知書交付となります。
消防法令適合通知書を入手するための申請書類の一例を以下に記載します。
①消防訓練実施計画報告書
②消防計画作成(変更)届出書
③消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書 ※設備の種類ごとに作成
④消防法令適合通知書交付申請書
⑤防火管理者専任届出書
⑥防火対象物使用開始届出書
⑦防火対象物点検結果報告書
以上の書類のうち、消防用設備等設置届出書には、設置や工事をした消防設備士・電気工事士の資格内容を記入する必要があります。つまり、防災業者等に頼んで設置・工事をしてもらう必要があるということです。そのため、事前相談の段階から業者を選定し、消防への相談にも立ち会ってもらわなければなりません。
簡易な申請方法
以上は一般的な申請方法なのですが、小規模な住宅については、条件を満たせばより簡易な申請が可能になります。
申請のどの部分が簡単になるのかというと、設備の設置を資格者に頼まなくても、自身で可能になるという点です。
特小自火報
通常、消防設備士による設置が必要な「自動火災報知設備」は、条件を満たすことで「特定小規模自動火災報知設備(以下、特小自火報)」という、工事が不要な設備を設置可能となります。設置できる建物の条件は、2階建て以下、建物の延べ床面積300㎡以下ならおおむね満たすと考えて良いです。条件の詳細は消防のホームページを確認する必要があります。
誘導灯の設置免除
また、本来なら電気工事士がするべき誘導灯(「非常口」などの表示)の設置も、条件を満たすことで不要となります。こちらは少し細かい条件となりますので、消防のホームページや事前相談でよく確認しておく必要があります。
まとめ
消防の申請は専門用語も多いうえに、業者に工事を頼むとなると100万円以上かかってしまうことも珍しくなく、民泊事業者にとっては大きな負担です。簡易な申請方法で申請可能な物件を探すことも、場合によっては必要になるでしょう。
次は、営業上の違いについて見ていきます。





