【民泊許可申請シリーズ④終】民泊と簡易宿所、営業上の違い
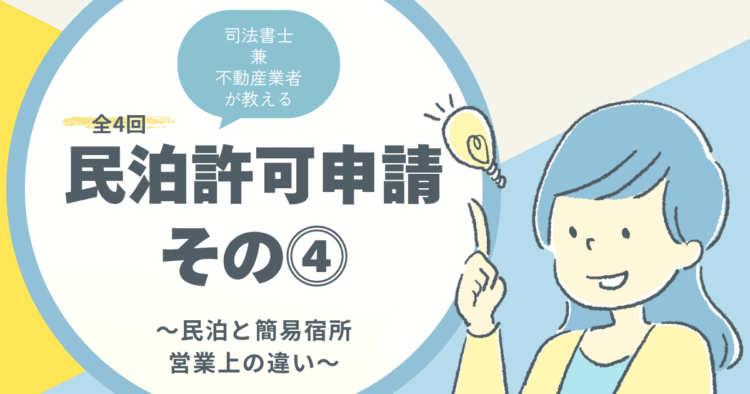
用途地域
まず、営業可能な「用途地域」の違いがあります。これは申請前というより購入・契約前に確認しておくべきことです。区市町村の窓口に電話して、該当地域で民泊・簡易宿所を行いたいが可能ですか? と聞けばすぐに教えてくれます。
旅館業が可能な地域は以下の6つです。自治体の公開しているサイトでも調べることが可能ですので、物件を決める前に見ておきましょう。
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・商業地域
・近隣商業地域
・準工業地域
なお、民泊新法による営業は、工業専用地域以外であればどこでも可能となっています。しかし、自治体によって制限が掛けられている場合がありますので、やはり事前に確認した方が無難です。
営業上における一番大きな違いは、年間180日以上の営業が可能かどうかという点です。
民泊新法による届出の場合、年間180日しかゲストを宿泊させることができません。
一方、簡易宿所の許可を受ければ、この制限はなくなりますので、より多くの売上を見込むことができます。
民泊と簡易宿所の申請の難易度と、ゲストの宿泊日数の見込みをよく考えて、どちらで申請するか考えておきましょう。
建築確認届出が必要か
建物には建築当時に定められた「用途」があり、それを変更するには自治体に届出を出さなくてはいけません。戸建て住宅の用途は言うまでもなく「住宅」です。
民泊新法の場合は「住宅」のままで営業が可能なのですが、旅館業を申請する場合は、用途を「旅館」に変更する必要があります。
ただし、民泊として使用する部分の底面積が200㎡以下の物件は用途変更の建築確認届出手続きが不要となっています。確認申請が必要になった場合、古い物件ですと現在の法律に適合させるための大規模な工事が必要となることもあります。建築基準法は日々改正されており、場合によっては用途変更をすると違法建築物となるため、旅館には変更できないということも起こり得ます。建築確認が必要になると手間と時間が倍増しますので、物件が200㎡を超えていないかどうか、確認しておいた方が良いでしょう。
まとめ
これまで4回にわたって民泊許可申請の詳細を見てきましたが、いかがでしたでしょうか。
書類を揃えるのも大変なのですが、本当にその物件で許可が取れるのか、購入・契約前に判断することのほうが大切で難しいです。民泊は関係法令が多く、役所も横断的に把握しているわけではないため、自ら調査に動くことが大切です。





